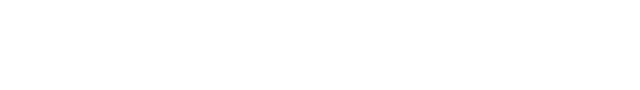カテーテルアブレーションの新時代:パルスフィールドの強みと弱点
先日、広島西部地区の講演会にてディスカッサーを務める機会をいただきました。循環器開業医の視点から、心房細動への取り組みについてお話ししました。
久しぶりに中野教授の講演を拝聴し、大変有意義な学びの機会となりました。近年、カテーテルアブレーション治療にパルスフィールドアブレーションという新たな選択肢が加わり、アブレーション治療の「ゲームチェンジャー」として注目を集めています。
各社で形状が異なるパルスフィールド
パルスフィールドアブレーションは、短時間の高電圧パルスにより電場を発生させ、細胞膜に不可逆的な穿孔を生じさせることで細胞死を誘導する治療法です。熱的影響に依存しない点が特徴で、心筋細胞を選択的にアブレーションできるため、食道や横隔膜などの周辺臓器への損傷を抑え、合併症のリスク低減が期待されています。
カテーテルアブレーション治療には、従来の高周波アブレーションに加え、近年ではクライオアブレーションが広く普及しています(ホットバルーンやレーザーアブレーションもありますが、実施施設は限られています)。そして、昨年よりパルスフィールドアブレーションが導入されました。
左から順に、高周波 (RFA)、クライオ (CYRO)、パルスフィールド (PFA)アブレーション
以下、それぞれの手技の特徴や違いについて、一部私見を交えながらご説明します。
- 高周波アブレーション (Radiofrequency Catheter Ablation, RFCA)
概要
高周波電流を利用して、心筋組織を加熱(約50~70℃)し、異常な電気信号の伝導経路を焼灼します。
最も広く使用されているアブレーション技術で、心房細動、発作性上室性頻脈、心室頻脈などに適用されます。
メリット
・高い成功率: 心房細動や上室性頻脈の治療で長年の実績があり、成功率は心房細動で70~90%(初回手技)。
・精密な焼灼: ポイントごとの焼灼が可能で、複雑な不整脈の治療に適している。
・幅広い適用: さまざまな不整脈に対応可能。
・技術の成熟: 長年の臨床データと経験に基づく信頼性。
デメリット
・熱による組織損傷: 周辺組織(食道、肺静脈、横隔神経など)に熱損傷を与えるリスクがある。
・手技時間: 近年の新たなテクノロジーと比較して手技時間がやや長い。
・血栓形成リスク: 焼灼部位での血栓形成や塞栓症の可能性 (頻度はごく稀)。
・合併症: 血管損傷、心タンポナーデ(0.5~2%)、肺静脈狭窄(まれ)など。
高周波では半径2〜3mmのタグをつけながら肺静脈を囲うように焼灼 (J&J社のCARTO system)
- クライオアブレーション (Cryoablation)
概要
極低温(約-50~-80℃)を用いて心筋組織を凍結させ、異常な電気信号の伝導経路を破壊する。
主に心房細動の肺静脈隔離に用いられるが、施設によっては心房粗動や後壁隔離にも適応。
手技が比較的簡便で、手技時間も短く行うことができる。
メリット
・安全性: 熱を使用しないため、食道損傷リスクが低い。
・均一な焼灼: クライオバルーンは肺静脈の入口全体を一度に凍結でき、均一な焼灼が可能。
・手技時間の短縮: 特に肺静脈隔離において、高周波より手技時間が短い。
デメリット
・適用範囲の制限: クライオバルーンは主に肺静脈隔離に特化しており、複雑な不整脈には不向き。
・再発率: 高周波と同等またはやや高い。
・横隔神経麻痺: 一時的な横隔神経麻痺のリスク(1~2%)が高周波と比べやや高い。
クライオではバルーンを肺静脈に押し当てて冷却し、一度に肺静脈隔離を完成させます
- パルスフィールドアブレーション (Pulsed Field Ablation, PFA)
概要
高電圧の短時間パルス電流を用いて、心筋細胞の膜に不可逆的な電気穿孔(エレクトロポレーション)を引き起こし、組織を破壊する。
非熱的アブレーション技術として注目され、心房細動の治療で急速に普及しつつある。
メリット
・非熱的: 熱を使用しないため、食道、肺静脈、横隔神経への損傷リスクが極めて低い。
・高い安全性: 周辺組織への影響が少なく、合併症率が低い(心タンポナーデや塞栓症のリスクはほぼない)。
・短い手技時間: 通常1~2時間で完了し、効率性が高い。
・成功率: 初期データでは心房細動の成功率はクライオアブレーションと同程度。
デメリット
・新しい技術: 長期的な臨床データがまだ不十分。
・適用範囲: 現時点では主に心房細動に使用され、他の不整脈への適用はない。
パルスフィールドでは、熱を使用せず、短時間に肺静脈隔離を完成させます
近年、クライオアブレーションを主に実施していた医療施設では、パルスフィールドアブレーションへの移行が進んでいる傾向が見られます。i-gelを用いた全身麻酔下での治療により、患者の負担が軽減され、手技時間の短縮も可能なことから、普及が進んでいる理由の一つと考えられます。市内の多くの病院では、初回の心房細動アブレーションでパルスフィールドアブレーションを実施するケースが増えています。
一方で、パルスフィールドアブレーションには課題もあります。従来の高周波アブレーションでは、初回治療の成功率(1回の治療で不整脈が再発しない割合)は、発作性心房細動で85〜90%、持続性で70〜80%、長期持続性で60〜70%程度です。クライオアブレーションは高周波アブレーションと比較して非劣勢であることが示されており、パルスフィールドアブレーションもクライオアブレーションと同程度の成績が報告されています。ただし、日本での治療成績や長期的なデータはまだ十分ではなく、今後のさらなる検証が期待されます。
発作性心房細動 (PAF)の1年後の成績:洞調律維持はPFAとクライオでそれぞれ80.3% vs. 83.1%
非発作性心房細動 (持続性と慢性)の1年後の成績:洞調律維持はPFAとクライオでそれぞれ66.8% vs. 71%
心房細動の発生源は80〜85%が肺静脈に由来するため、両側肺静脈隔離術が心房細動アブレーションの標準的な手法とされています。しかし、残りの15〜20%は心房内や上大静脈に起因します。そのため、薬物負荷による起源の同定は重要であると考えております。パルスフィールドアブレーションでは、薬物負荷や起源の同定が難しいため、肺静脈隔離を目的とした初回手技には適していますが、肺静脈起源かどうかを判別しながら進めることはできません。
広島総合病院および尾道総合病院では、高周波アブレーションを中心に治療を行っています。施行する不整脈担当医師は長年にわたり高周波アブレーションの経験を積んでおり、確実な隔離ラインの作成に優れています。薬物負荷による不整脈誘発率は約60%ですが、初回アブレーションで肺静脈起源が明らかになる場合もあり、高周波アブレーションの利点が活かされる場面があります。手技時間はパルスフィールドアブレーションに比べやや長くなるものの、患者とオペレーターの双方が納得できる治療を目指しています。
修練を積み高周波アブレーションにて肺静脈隔離を完遂するレジデントドクター
中野教授とお話ししましたが、高周波アブレーションが現時点で最も汎用性が高く、信頼性の高い手技であることを再認識しました。パルスフィールドアブレーションは多くの可能性を秘めており、今後さらに普及していくことは間違いありません。しかし、不整脈医がこれまで培ってきた技術や経験が最も活かされるのは高周波アブレーションであり、今後も手技の中心に位置するのではないかと予想しています。
アブレーション治療の課題やニーズに対応するため、パルスフィールドと高周波の両方の機能を備え、高解像度マッピングが可能なカテーテルの開発も進んでいます。これにより、治療部位に応じた最適なエネルギー選択が可能となり、合併症を抑えつつ、より柔軟な治療戦略が実現する時代が期待されます。
Affera™ Mapping and Ablation システム (メドトロニック社)
当院では、基幹病院と連携し、不整脈治療に取り組んでいます。アブレーション治療は重要な選択肢ですが、不整脈治療はそれに留まりません。再発予防のためのリスク管理や、経過観察を通じた再発の早期発見も欠かせません。患者が安心して日常生活を送れるようサポートすることを目指しておりますので、不整脈に関するご相談があれば、ぜひ当院までご連絡ください!