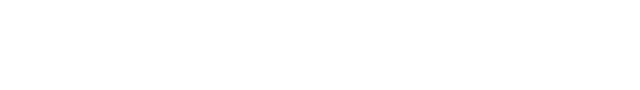2025年6月の1枚 (Sly & the Family Stone)
Sly & the Family Stone
『There’s a Riot Goin’ On』(1971年)
ソウル・ファンクの神様、スライ・ストーン(シルヴェスター・スチュワート)が82歳で逝去されました。そのわずか2日後には、ブライアン・ウィルソンまで。言葉では表現しきれない深い悲しみが胸を締め付けます。両者はそれぞれの音楽的才能を通じて、アメリカの音楽文化の発展に多大な貢献を果たしました。
スライはソウルそしてファンクというジャンルを確立した先駆者であり、音楽史に与えた影響は計り知れません。本日は、Sly & the Family Stoneの歴史的名盤『There’s a Riot Goin’ On』をご紹介いたします。
星条旗の再構築を暗示したジャケット
邦題『暴動』が示すように、このアルバムは激動の時代を背景に生まれました。1960年代後半の公民権運動や反戦運動の高揚感から一転、1970年代初頭のアメリカは政治的混乱、麻薬問題、ベトナム戦争の泥沼化など、暗い空気に覆われていました。本作は、そうした社会の不安や失望を映し出した作品です。タイトルは、マーヴィン・ゲイの『What’s Going On』への皮肉なアンサーとも解釈され、楽曲には希望よりも疲弊や混乱が色濃く表れています。
前作『Stand!』(1969年)では団結を呼びかけるメッセージで大成功を収めたスライでしたが、その後はレコード会社やブラックパンサー党、黒人解放運動家からの圧力、そしてドラッグ依存により、精神的・肉体的に大きなダメージを受けていました。この混乱の中、バンドメンバーの多くがレコーディングを拒否したため、アルバムに収録された楽曲のほとんどのパートをスライ自身が演奏しています。
本作は、ファンク、ソウル、ロック、ブルース、そしてサイケデリックな要素を融合させた革新的なサウンドが特徴です。ファンキーなリズム、ダークでムーディーな音色、そしてオーバーダビングを駆使したローファイな質感が、アルバム全体に独特の雰囲気を生み出しています。スライの不安定な精神状態は、断片的で散漫な歌詞や不規則なリズムに反映され、バンドの分裂は、従来のタイトなアンサンブルから孤立したソロプロジェクトのようなアプローチへと変化しました。
タイトル曲は「0秒」の無音
ドラムマシンの使用やローファイな音質は、スライが制作のコントロールを維持しようとした苦悩の結果であり、同時に彼の内面的な混乱が音を通して映し出されたものでもあります。この壊れた美学は、アルバムを単なる音楽作品を超えた存在に昇華し、リスナーに深い感情的共鳴を与えます。
本作のサウンドは、現代の音楽プロダクションにおいても新鮮であり続けています。ローファイな質感や実験的なアプローチは、ビリー・アイリッシュやフランク・オーシャンといった現代のアーティストにも影響を与え、継承されています。
USオリジナル盤 (色合いやトリミングがUK盤と異なる)
この『暴動』は、現在のアメリカ社会の混沌やトランプ政権の強硬な姿勢とも共鳴する要素を持っているように感じられます。アルバムが描く失望や混乱は、トランプ政権の強権的な政策や、それに対する市民の抗議運動に見られる社会の分断と重なります。スライが音楽で表現した「壊れた美学」や既存の制度への不信は、トランプが「ディープステート」に立ち向かい、既存の秩序を再構築しようとする姿勢と通じるものがあるかもしれません。
しかし、トランプ政権のアプローチは、権力の集中や保守的な価値観の強調、そしてグローバリズムへの強硬な反発を伴うため、賛否両論を呼んでいます。この混沌が社会を収束させるのか、それともさらなるさらなる「暴動」を引き起こすのか、注視する必要があります。これは日本の私たちの生活にも関わる大きな問題です。
スライの音楽は、「愛国心を持ちなさい」と訴えかけているようにも聞こえます。これは、多民族国家であるアメリカに限定されるメッセージではありません。愛国心の共有がなければ、移民との共生は困難です。日本においても、未来を切り開くためには、自身のアイデンティティを再確認し、母国に誇りを持つことの重要性を、スライの音楽は教えてくれているようです。
レコードに針を落とせば、そこには想像を超える世界が広がっています。彼の作り出したこの音楽は、我々の心に永遠に火を灯し続けることでしょう。
R.I.P. Sly Stone (Sylvester Stewart)